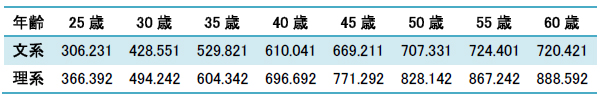男性は、2006年ごろから少なくとも九回献血しており、日赤が男性の血液を調べたところいずれも抗体陽性だった。6月の献血は血液製剤メーカーや医療機関への出荷を差し止めたが、過去の献血を基につくられた血液製剤11本が8医療機関で10人程度の患者に輸血された可能性があることが判明。厚労省と日赤は患者の特定や感染の有無の調査を進めている。(読売新聞)
シャーガス病は、中南米に生息する吸血性のカメムシ(サシガメ)が人の血を吸う時、カメムシの糞に存在する原虫(トリパノソーマ)が人の粘膜や傷口などから体内に入ることで感染する。10~20年は症状がないまま推移するが、心臓が徐々に肥大し、心臓破裂で死亡することもある。中南米ではマラリアに次いで深刻な熱帯病とされ、二千万人以上の患者がいると推定されている。国内にこのサシガメは生息していないが、出稼ぎ日系ブラジル人などが潜在的感染者と考えられ、今回のような献血や臓器移植などで、感染が広がる可能性がある。